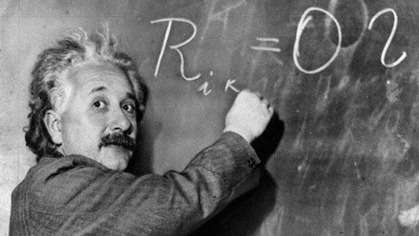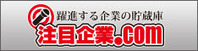『例えばなしの量と質』 ~コミュニケーションスキルアップ編~
『理論的には正しいと思うことでも、
感覚的にそのことがわからないと現場は抵抗する』
いつどこでインプットしたのかは忘れましたが、私のiPhoneにメモが残されているフレーズ。
なぜ、メモを残すのか??
それは、そのフレーズに共感する部分があるからです。
この内容は、私がトップ&リーダークラス対象の講演や研修を行う際にも
お伝えしている内容でもあります。
組織のトップやリーダーであれば、社員や部下や後輩に何かを伝えることで、
その組織やチームを良い方向に導いたり、自分の思い通りに動いてもらったり
するスキルが必要になるわけですよね。
かつて、学校では成績優秀で、社会人になってからも勉強をし続けて、
あらゆることに対する理論はわかっているはずなのに・・・
なぜか、まわりとうまくいかず、あげくのはてにはまわりからの抵抗にあう![]()
![]()
![]()
「なぜそんなことになってしまうのだろうか?」という相談を受けることもちょこちょこあります。
まあ、相談をするということは、自分のそんな現状に気づいて、改善していきたい
という意思を持っているということでしょうから、まだよいのかもしれません。
しかし、自身が上記のような状態で、まわりから信頼・信用を得られていないということに
気づいていないトップ&リーダーが実はかなり多いのも事実。
皆さんのまわりにも思い当たる方がいるかもしれませんよね~![]()
![]()
理論を学ぶことはもちろん大切なことだと思うのですが、
それよりも大切なことがあると思うのです。
立場が上になればなるほど『人間を学ぶ』ことがより必要になる!!
そう思うのです。
理論だけで人を動かせると思うのは大間違い。
理論は人を理解させることはできても、人の動力のスイッチを入れるツールにはならない。
「人間を学ぶ」ことができていない”理論だけ人間”は、絶対に組織やチームの
マネジメントの質を高めることはできない!!
そんなところでしょうか![]()
![]()
例えば、相手に理論や理想論を得意げに自慢げに一方的に話した後に
「皆さん、わかりましたかっ!!」 「お前たち、わかったなっ!!」
なんて誇らしげに語る方々も見かけますが、多くの聞き手はそんなときにどう思っているか??
「なんとなくわかったけれど、だから何?」
「その内容が、自分の仕事や生活とどんな関係があるわけ?」
そんな感じではないでしょうか![]()
![]()
![]()
そして、そんなことがいつものように再現されると、聞き手は、
「あの人はまったく現場のことや我々のことがわからず、理論ばかりで・・・」ということで
信用されず、最終的には抵抗されるようになるのかもしれませんね![]()
![]()
自分もそんなふうに思われる職業なのかもしれませんが、
少なくとも、個人的にはそうならないように意識しているつもりです![]()
![]()
人は、その内容に感覚的に具体的に
納得したり、共感したりすることで動力スイッチが入る
と思っています。
だから、理論に何かを付け足して、
相手が感覚的に具体的にその内容を
リアリティー化できる情報に転換してあげること
がポイントになるのです。
では、聞き手がリアリティー化する情報に転換するためには??
いろいろな方法はあると思いますが、今回はその中の1つだと思っていることを
お伝えします。それは・・・
『例えばなしの量と質』
そんな簡単なことですか??なんて思う方も多いかもしれませんが、
この「例えばなし」は、相手に何かを伝達する際のとても重要な素材なのです。
個人的には、「例えばなし」を相手に合わせて巧みに使いこなせるスキルを持っている人こそ
コミュニケーションレベルが高い人だと認識しています。
私がかつて在籍していた船井総研では、「事例を集める」という言葉で教わりました。
若いうちから講義で理論を語るべからず。
若いうちには、あらゆる成功事例・失敗事例を集めて、整理整頓してお客様に伝えるべし。
「例えば、あの会社では・・・」
「例えば、あの社長は・・・」
「例えば、この業界のトップ企業10社の特徴を整理してみると・・・」
「例えば、この商材の売れ筋価格は・・・」
現場の事例をたくさん持っていることで、自分より年上の方々が私の話に耳を傾けてくれたり、
若くても信用してくれたり・・・今となっては、とても大切なことを教えていただいたと実感します。
当時の勘違い部下には、「事例を持っていない若手なんて、誰にも相手にされないよ!!」
なんて言っていたものです。
理論だけ聞いて、「なんだかよくわからないな~」という状態の人が多い場合、
当然、それが動力に繋がらないわけですから、組織やチームとしては資源を十分に
活用できていない状態なわけです。
だからこそ、トップ&リーダーは、「なんだかよくわからないな~」という人達を
「それならよくわかります。頑張れそうです!!」という状態に導くスキルが求められる
わけですよね。
その人のライフスタイルや仕事にもよりますが、
日々の生活の中では、たくさんの老若男女を相手にすると思います。
ですから、あらゆる人達にわかりやすい「例えばなし」を使いこなせるように
日々アンテナを張って情報をインプットすることが大切ですよね。
日々のインプットの量と質が、「例えばなしの量と質」に連動している
と言っても過言ではないと思います。
どんな相手にもあらゆる場面にも対応するために「例えばなし」のラインナップを増やす。
相手に合わせて、その人がわかりやすい的確な「例えばなし」をセレクトできる。
それが『例えばなしの量と質』という意味です。
ふと考えてみると、話がわかりやすい人は、「例えばなし」を多様していることに
気付くのではないでしょうか。
理論だけでは人は動かない。
理論にちょっと「例えばなし」を付け足すことは、相手に対する思いやりを付け足すこと
なんだと思います。
本日は、コミュニケーションスキルアップ編ということで、何かにお役に立てばと
「例えばなしの量と質」について少し整理してみました。
そう言えば、先日、『CLP代表取締役 雑賀竜一』として取材を受けた記事が
以下のWEBマガジンで掲載されていますので、クリックしてご覧下さい。
★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 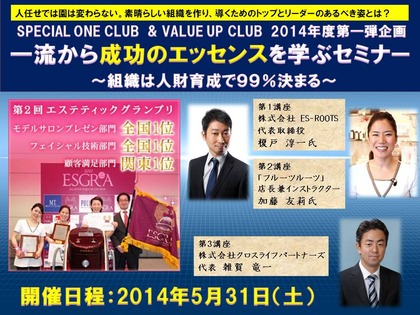
詳細はこちらから
まだまだ、残席ありますのでお申込お待ちしております。
★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★